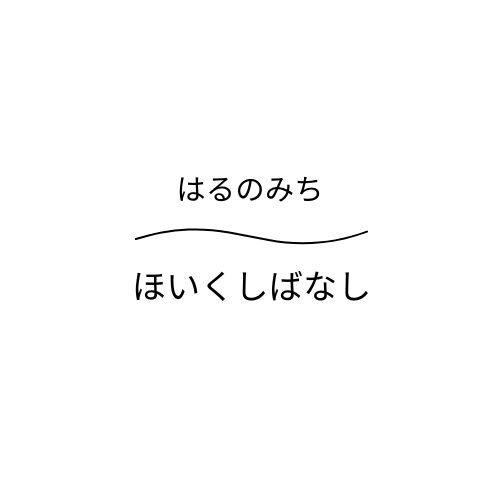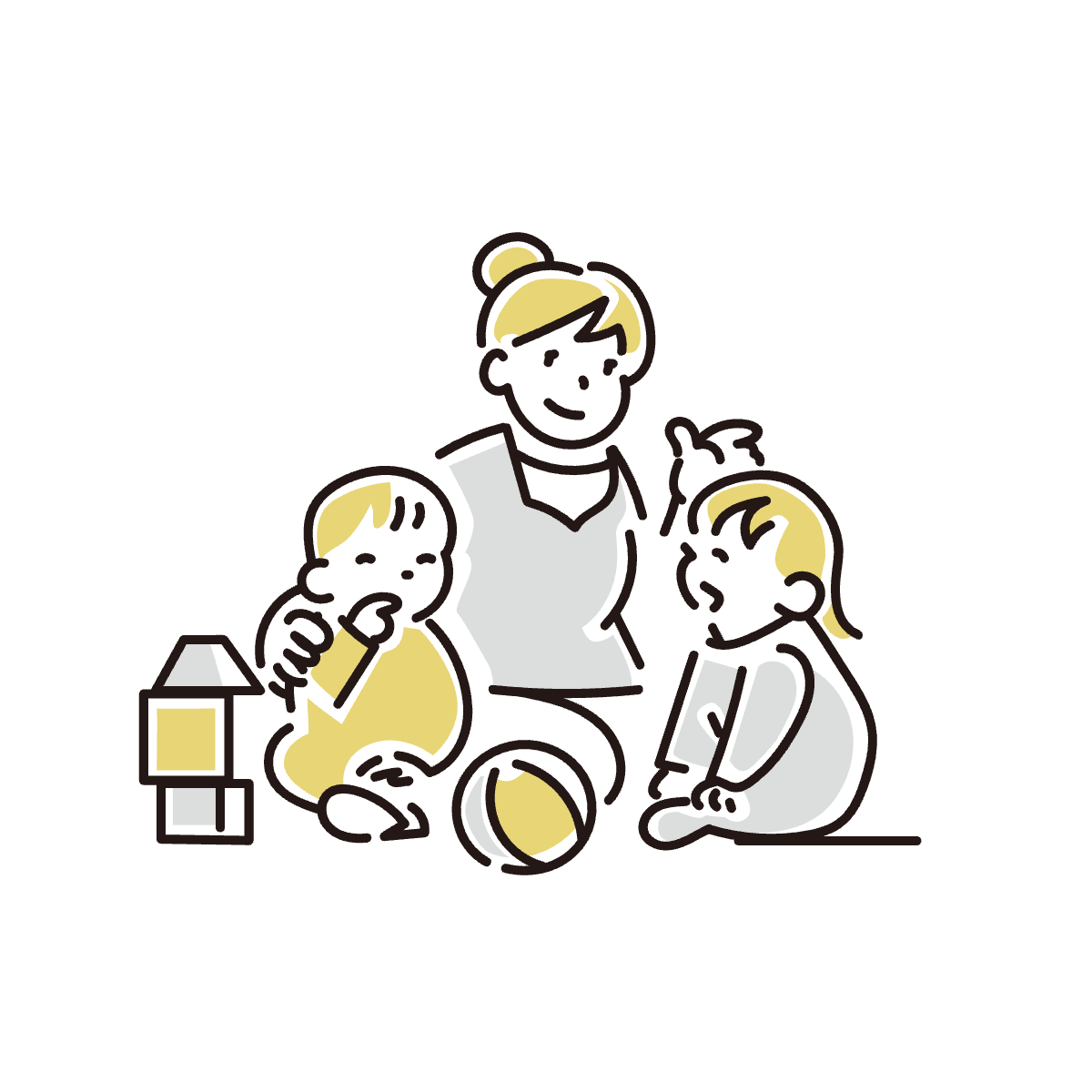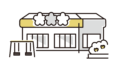どんなエプロンを買えばいいの?と悩むあなたに!
保育士の仕事着として、エプロンを着用している方も多いですよね。
園から指定されたものを身に付けることもありますが、自分で用意することもあります。
ちなみに私が働いた4園中、3園は自分で用意したものを着用していました。
中には、領収書を提出すれば、被服費として年間数千円補助が出る園もありましたよ。
毎日身に付けるものですから、使い勝手や見た目も大切ですよね。

そこで、実際に仕事着として毎日使用してわかったエプロン選びのポイントを挙げてみることにしました!
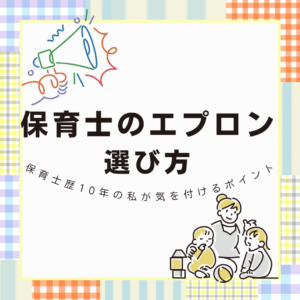
1.園の決まりを確認する!
大前提ですね!必須です!
園によっては、キャラクターものがNGであったり、素材や色の指定があったりと、様々なルールがあるかと思いますので、購入前に、まずはしっかりと確認しましょう!
暗黙のルールのようになっていることも多いため、紙ベースの規則を見て判断するよりも、先輩職員に口頭で確認するのが確実だと思います。

機会があれば、その園の保育士がどのような格好で働いているかも、実際に見てチェックしたいですね!
2.ポケットは深いもの!
これも大切!エプロンのポケットはなにかと使います。
ティッシュやメモ帳、体温計、お散歩中に連絡がとれるようにするための携帯電話、子どもから預かった落ち葉などなどを入れて、しかも私たちは激しく動くのです!
立ったり座ったり走ったり踊ったり、子どもと一緒に寝ころんだりすることもありますよね。
浅いとすぐに落ちてきます。一応入るな~くらいでは落ちてくるのです。
なるべく深い物を選びましょう。
保育中にポケットから物が落ちてくると、子どもの注意が逸れたり、誤食等の危険があったり、また、メモなどを落とすと情報の流出に繋がる恐れもありますよね。※ポケットに入れるようなメモは、落としても問題のない内容に!
園によっては、それらを保育中に持ち運ぶ場合は、口が閉まるポーチに入れてからポケットに入れることや、小さな斜め掛け鞄に入れるなど、独自のルールが定められていることがありますので、そのあたりもチェックしたほうが良さそうです。

もしルールがなくても、個人でしっかりと安全管理をしていきましょう!
3.着脱が簡単なもの!
現場の保育士が使っているエプロンは、頭から被るタイプの物が多いですね。
私もやはり、背中で紐を結ぶよりも、着脱が簡単な被るタイプをおすすめします。
例えば、食事用のエプロンに替えるとき、エプロンが汚れてしまったとき、掃除をするときなどなど、園や場面によって様々ですが、1日のうちにエプロンを着脱する機会は意外とあります。そして、保育に支障が出ないよう、手早くしたいことも多いのです。
ちなみに、被るタイプのものは背中が隠れるのも嬉しいポイント。
子どもと一緒に激しく動いたり、前かがみの姿勢になっていたりすると、“背中が出てしまっていないかな”と気になるものですが、被るタイプのエプロンを着ていれば心配ご無用!

体のラインが隠れるのも嬉しいです!
4.丈は長すぎないもの!
丈が長く、ワンピースのようでシルエットが可愛いものもあります。
しかし、床に座っている姿勢から立ち上がるときに、自分の膝でエプロンの裾を踏んでしまってスムーズに立ち上がれなかったり、体操などで四つ這いになるときに邪魔になったりすることも……。
これでは保育着として困ってしまいますよね。
丈の長さは、太ももの半分くらいが目安かなぁと思います。
おしりが余裕をもって隠れるくらい。

自分にぴったりの、動きやすい丈の物を探してみてください!
5.せっかくなら、子どもが好きなもの!
シンプルでカフェデザイン的なおしゃれエプロンも、好きです。
活動中、子どもの集中を邪魔することもないですしね!
しかし私は、エプロンを使って子どもと関わるのも好きなのです!
子どもが持っているものを預かるときに、エプロンのポケットにうさぎが描かれていれば、「うさぎさんに”どうぞ”する?」と誘ったり、
お昼寝から起きたばかりでまだ眠そうな子どもに、「バスも○○くんおはようって言ってるよ」と、エプロンの胸のところに描かれたバスを動かしてみたり、
などなど、日常のちょっとしたときに活躍してくれます。
子どもの方から「これは?」「(はらぺこ)あおむしだ!」などと興味をもって、関わりが生まれたりもしますしね。

まだ子どもと信頼関係が築けていない新しい環境でこそ、キャラクターエプロンに頼ってみるのも良いと思います!
以上、実際に保育をしていて感じる、エプロン選びのポイント5つご紹介しました!
人や園によってそれぞれの基準があるかと思いますので、ご参考までに。
自分が気に入ったエプロンを身に付けると、気持ちも明るくなりますよね!
エプロン探し、ぜひ楽しんでください♪